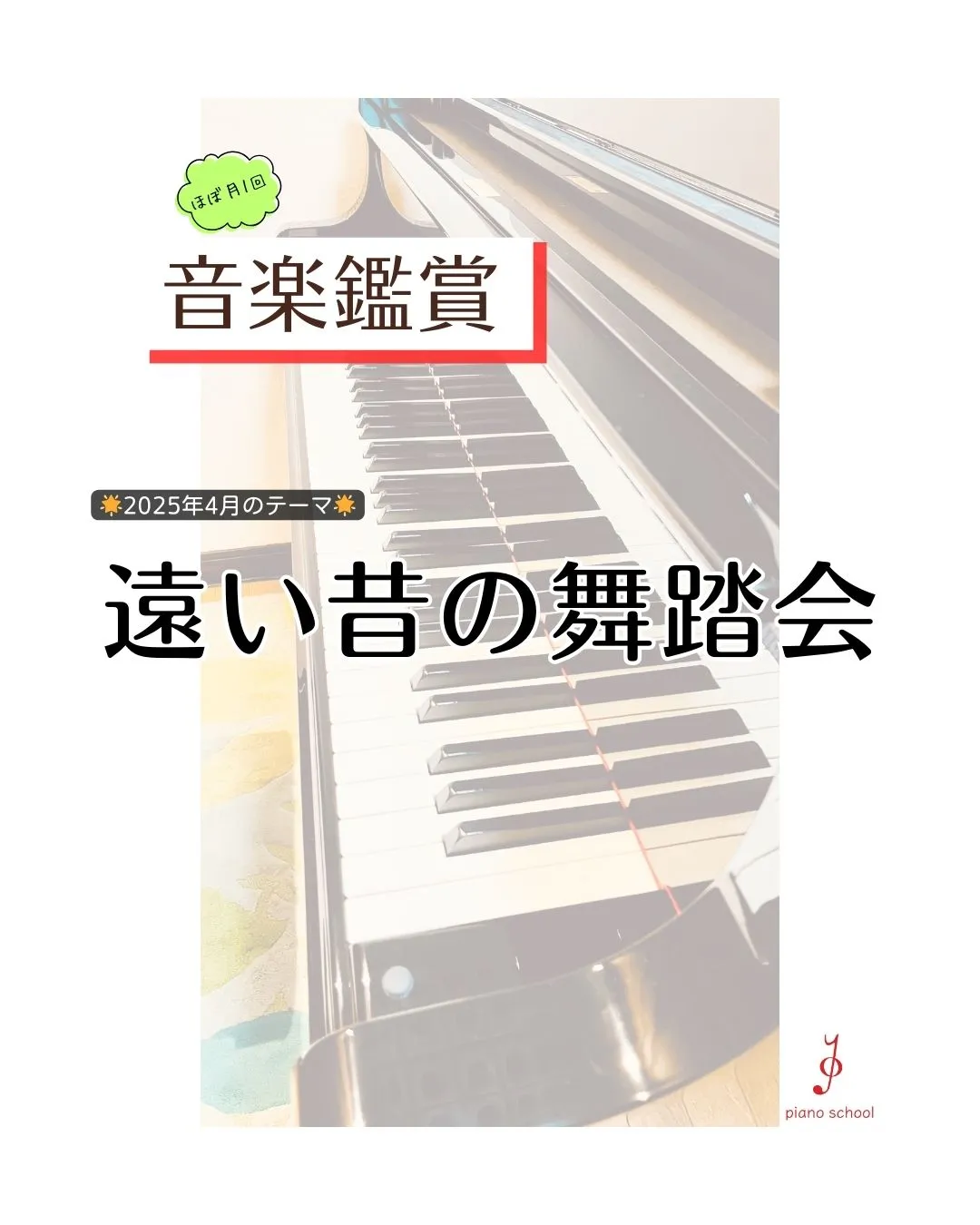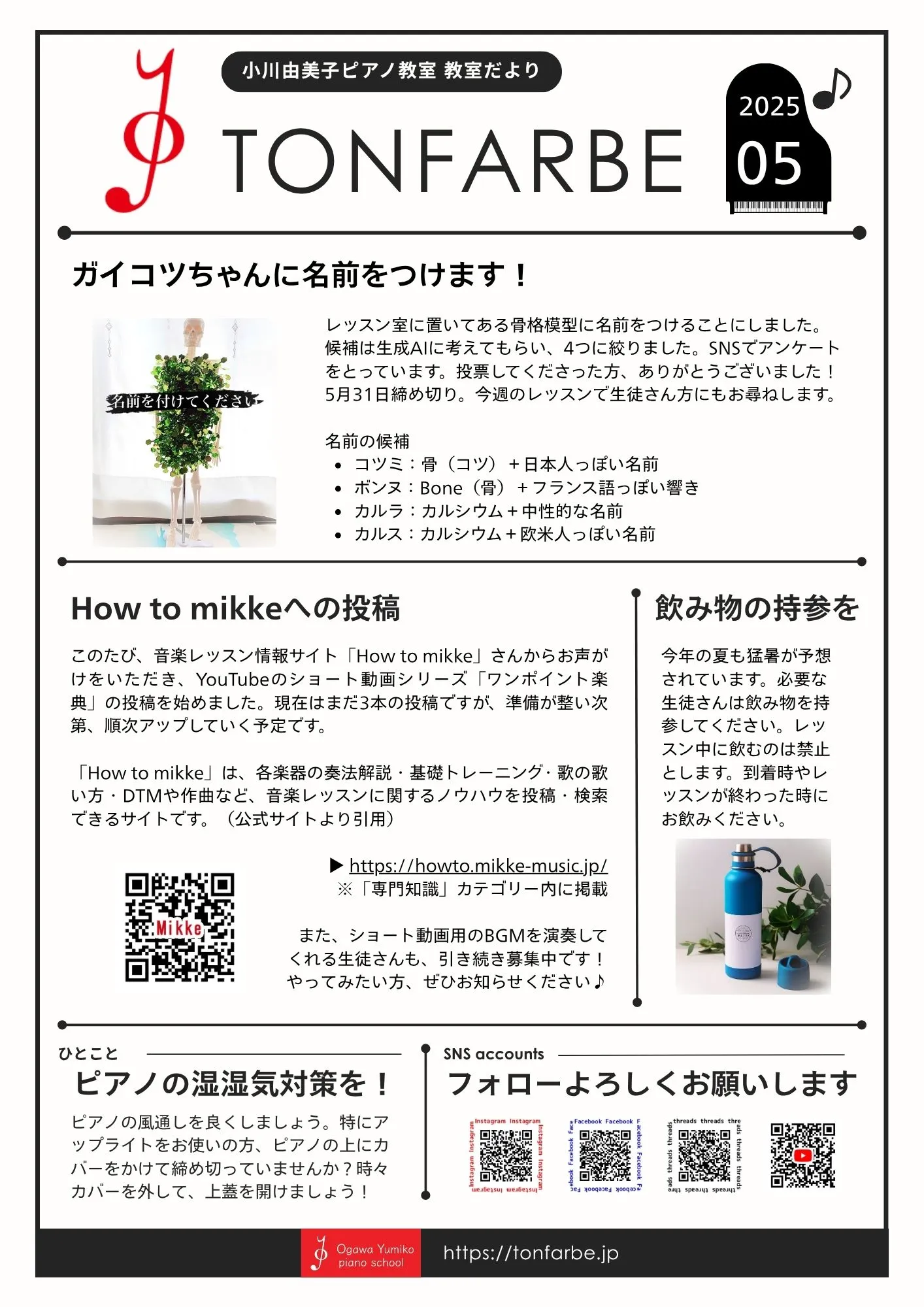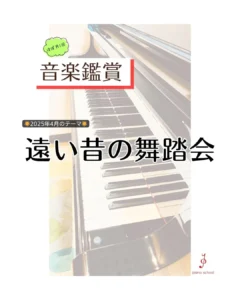
4月と5月の音楽鑑賞は、“遠い昔の舞踏会”をテーマに選曲。モーリス・ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」を聴きました。4月にはピアノ版を、5月の連休明けにはオーケストラ版を聴きました。今年はラヴェル生誕150周年です。
タイトルに「亡き王女」とあると、少しもの悲しいイメージを持つかもしれませんが、決してお葬式の曲ではありません。ここで言う「亡き」とは、「かつての、遠い昔の」というニュアンスです。
パヴァーヌとは
「パヴァーヌ」は、16~17世紀ヨーロッパの宮廷舞踏。ゆったりとした2拍子(または4拍子)で、男女のペアが行列をつくり、行進するように踊るものでした。語源には、スペイン語で「クジャク」を意味する言葉や、イタリアの都市「パドヴァ」から来ているという説もあります。(曲によっては、少し速い3拍子の“ガイヤルド”が続くことも。)
亡き王女のためのパヴァーヌ
この曲は、1899年(ラヴェル24歳)に作曲したピアノ曲で、その後1910年にオーケストラ版に編曲しました。演奏時間はおよそ6分(オーケストラ版は7分)。ト長調・4分の4拍子。途中で短調へ変わりますが、最後にまたト長調に戻って終わります。
ラヴェル自身は、17世紀スペイン宮廷の画家、ディエゴ・ベラスケスが描いた「マルガリータ王女の肖像画」をルーブル美術館で見て、インスピレーションを得たとされています。まるでおとぎ話のような世界観です。
ラヴェルについて
1875年(明治8年)3月7日~1937年(昭和12年)12月28日。バスク系フランス人。*バスク…スペインとフランスにまたがっている地方。←バスク風チーズケーキのバスクですよ~!ファッションにものすごいこだわりを持っていました。
1932年、パリでタクシー乗車中の事故がもとで、晩年は記憶障害や言語障害などの後遺症に苦しむことになりました。
近現代の音楽について
主に20世紀の音楽。後期ロマン派と一部時代が重なります。新しい手法の音楽が様々な国でうまれました。一方でバロックや古典への“回帰”を求める作品も多くうまれ(新古典主義とも言う)、音楽の多様化が進みました。
“音楽の後進国”と言われた国々からすぐれた作曲家があらわれ、名作も多数うまれました。歴史背景としては、世界各地で近代化が進み戦争も多かった時代。飛行機や電話の発明、電車の開発、ディーゼルやガソリンで動くエンジンの開発など…現代の暮らしに近づいてきました。電子楽器の開発もこの時代に始まりました。ピアノが88鍵になるのは第一次世界大戦後。
この時代のフランスでは、芸術やファッションも大きく発展しました。ラヴェルが生まれる前後にはルイ・ヴィトン(1854年創業)エルメス(1837年創業)がすでに誕生しており、カルティエ(1847年創業)も王族の宝飾品を手がける存在に。そしてラヴェルの晩年には、シャネル(1909年創業)が登場し、モードの世界に新風を吹きこみます。
音楽もファッションも、洗練された感性を求めた時代だったのです。
【おまけ】1867年にはフランスで第2回目となるパリ万博が開催されていて、日本も初参加しています。今の一万円札でおなじみ、渋沢栄一さんもこの年フランスに行っています。